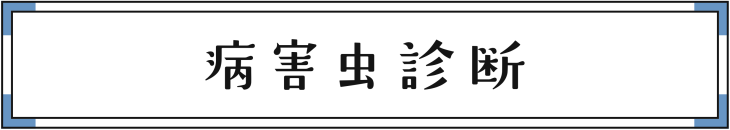ウドンコ病
ウドンコ病
特徴
麦類・ウリ科野菜・果樹など多くの作物に発生します。茎や葉の表面に,始めは白くて小さな斑点(菌糸)ができ,やがて分裂細胞がたくさんできて,うどん粉をまぶしたように白くなります。更に進むと病斑は灰色となり,その中に黒い小さな粒が現れます。この粒の中に「子のう胞子」が入っています。「子のう胞子」は枯葉や落葉について冬を越し次の年の発病の原因となります。
対策
発病適温は28℃前後,湿度は50~80%です。弱い光線を好み直射日光を嫌います。そのため,下部の葉に発生することが多く,風通しがよく乾燥していると発生しにくくなります。冬の落ち葉や枯葉,発生した葉を早めに処分しましょう。
葉かび病
葉かび病
特徴
トマトの葉の表面が黄色く変色し,裏面はビロード状のカビが生えます。下の葉から発病し上の葉に移っていきます。このカビの表面には多数の分生胞子が密生していて,風に飛ばされることでまん延します。定植から実の収穫まで長期間にわたって発生するので注意が必要です。
対策
発病適温は20℃~25℃,湿度95%以上の多湿を好みます。通気不良の場所で発生しやすいので風通しの良い場所で栽培しましょう。トマトの成長が止まった時に発生しやすいので,実が結実し養分がたくさん必要な時期に追肥をすることが大切です。
そうか病
そうか病
特徴
ジャガイモの表面にコルク化したかさぶたのような病斑(びょうはん)ができます。病斑は盛り上がったりへこんだり,網目状に亀裂が入ったりとさまざまです。地上部の発育は正常です。掘りあげた直後の病斑には,灰白色で粉状の菌糸,胞子がついています。
ラッカセイは花が咲いた後,葉の表面に1~2mmの褐色の斑点ができ,やがてコルク状に変化し,葉が内側に巻き込まれ萎縮(いしゅく)します。
対策
カンキツ類などにも発病します。ジャガイモは,新芽が出るころ雨で胞子を飛散させ病気を広げます。ビニルマルチ等をして感染を防ぎましょう。ラッカセイも花が咲いた後の雨に注意しましょう。
前年に発生したら,次の年は,種イモや植え付け前の土壌を消毒することが必要です。
いもち病
いもち病
特徴
イネの代表的な病気です。始めは,小さな暗い褐色の小さな病斑(びょうはん)ですが,やがて丸みのあるやや長方形の紡錘(ぼうすい)形の形になり,やがて病斑どうしがくっついて広がっていきます。苗から収穫の時期まで通して発生し,イネの各部位に発生します。発病した部分によって「葉いもち」,「節いもち」,「首いもち」,「枝こういもち」,「穂いもち」と呼ばれます。
対策
分生胞子や菌糸の状態で種もみ,わら,雑草などに付いて冬を越し,春に種もみが発芽する頃から活動を始めます。いもち病菌は25℃~28℃で湿気が多いと最も活動が活発になります。日照不足や低温下で発生します。窒素肥料を与えすぎるとイネの抵抗力が低下するので注意しましょう。
紋枯病(もんがれびょう)
紋枯病(もんがれびょう)
特徴
イネの水際部に暗い緑色で水に浸されたような病斑(びょうはん)が現れ,その後病斑の外側が褐色になり中央部の色が抜けて灰白色になって乾燥してきます。その後下葉から枯れ上がっていきます。水際が発病するとそこから上の部分に水が上がらず枯れてしまいます。
対策
早い時期に植えたり,苗と苗を密に植えたりすると発生しやすいので注意しましょう。薬剤を散布する時は,株の下の方に散布します。窒素肥料を多く与えすぎるとイネの抵抗力が低下します。
斑点細菌病(はんてんさいきんびょう)
斑点細菌病(はんてんさいきんびょう)
特徴
葉の気孔や傷から病原細菌が進入し,水に浸したような小さな斑点のような病斑(びょうはん)ができます。やがて黄褐色の病斑が葉脈に沿って広がり最後は灰褐色に変わります。
対策
発病最適温度は25℃,湿度が高いと発病しやすいので注意が必要です。病原菌は枯れた作物に付いて長期間生存します。病気になった植物体は畑の外で処分します。雨の後やかん水直後は植物に傷をつけないように注意しましょう。発病初期であれば薬剤散布が有効です。
灰色カビ病
灰色カビ病
特徴
褐色の病斑(びょうはん)ができ,その後灰色のカビが葉や果実に発生します。レタスは,葉の縁に発生し,葉脈に沿って,くさびのような形で病斑が広がります。
対策
20℃前後の低温で多湿のときに発生しやすいため,イチゴは夜間の保温に努めましょう。レタスは,肥料をやりすぎて軟弱で徒長した苗に発生しやすいので注意が必要です。発生後はかん水のし過ぎに注意しましょう。発生後放置すると被害が広がるので病気が出た花や実,葉等は取り除きましょう。
密植はさけて,マルチをして土壌からの水蒸気の発生を防ぐのが発生を防ぐポイントです。
斑点病
斑点病
特徴
周囲が紫色で斑点は褐色となります,病斑(びょうはん)が拡大すると灰褐色から暗い褐色の円形になり周囲が黄色く変色します。その後黒い粉のような胞子が発生します。
対策
葉の表面がぬれていると病気になりやすくなり,下葉での発生が多いので,かん水は根元にやることが大切です。日当たりと風通しの良い場所で栽培しましょう。梅雨の時期は注意が必要です。被害が出たら病斑のある葉や枝を切り取って処理をしましょう。
アブラムシ
アブラムシ
特徴
野菜や果樹の枝や若葉に付き,集団で汁を吸って,若葉をしおれさせたり,変形させたりします。また,ウイルスによって発生する「ウイルス病」を媒介します。トマト,キュウリ,レタスなどでは,「モザイク病」を媒介します。また,ふんが「すす病」の発生源になります。
ウメやモモなどのバラ科の果樹の芽に産みつけられた卵で越冬します。春になるとふ化して,ダイコン,キャベツ,ウリ科の野菜,ナス,草花類に移って初夏から秋まで世代交代を繰り返します。
対策
細かい防虫ネットで覆うなどの物理的防除,発生時の薬剤散布などの科学的防除を行います。ミナミテントウ,ヒラタアブ,クサカゲロウ,アブラコバチなどの天敵を使う生物的防除もあります。
栽培ほ場周辺の雑草はしっかりと除草しましょう。
ハモグリバエ
ハモグリバエ
特徴
施設栽培では一年中発生しますが,野外では冬は発生しません。親ハエが葉に卵を産むと2~3日でふ化し,産卵したあととウジが食害したあとが小さな病斑になります。その後ウジは葉の中に潜り込んで食害をおこし,食害のあとが線になって残ります。幼虫の寄生は下部の葉から上部の葉に進んでいきます。
対策
気温が25℃で卵から成虫までの世代の入れ替わりが16日周期となります。
寄生のない健全な苗を選んで定植することが大切です。施設では,不織布などで覆ってハエの侵入を防ぎます。発生初期の薬剤散布が有効です。黄色の粘着リボンを使って飛んでいるハエの発生を見つけます。
ハダニ
ハダニ
特徴
肉眼では見ることが難しい小さなダニで,たくさんの種類がいます。葉の裏側に寄生することが多く汁を吸った跡がかすり傷状に白く残ります。クモの仲間で野菜,花,果樹,花木に広く寄生します。被害が進むとクモの巣状の網を張ることもあります。
対策
高温で乾燥した環境を好みます。湿気が苦手なため,梅雨明けから発生することが多いので,葉の裏を注意して観察しましょう。ときどき葉の裏にスプレーで水を散布すると予防できます。株の間隔をあけて風通しを良くしておきましょう。
テントウムシダマシ
テントウムシダマシ
特徴
ナスやジャガイモなどナス科の野菜の害虫です。成虫とともに多数のとげをもった幼虫が葉の裏から食害を行います。食害をされたあとは,葉脈だけが残り網の目状になります。年に2~3回発生するので注意しましょう。
対策
成虫,幼虫ともに見つけたら捕殺します。収穫後の作物は畑に残さないで処分し,増殖するためのすみかをなくします。枯葉の下や木の樹皮の割れ目などで冬を越します。畑とその周辺の掃除をしっかりとしましょう。
カメムシ
カメムシ
特徴
とてもたくさんの種類がいます。口がストローのような形をしていて,葉や茎,果樹など口を差し込み,汁を吸います。イネの害虫ではアオクサカメ,クロカメムシ,ミナミアオカメムシ,コバネヒョウタンナガカメなどがいて,葉や茎から汁を吸います。若い籾(もみ)から汁を吸われると米粒が茶色に変色します。カキやナシなどの実に飛来するカメムシはスギやヒノキの実が豊作の年は冬を越える成虫が多く,大量発生するといわれています。
対策
周辺の雑草より成虫が飛んできます。薬剤散布が有効ですが,カメムシの種類により使用する薬剤が異なります。コンテナ等で栽培する場合は防虫ネットで覆う物理的防除も良いでしょう。栽培ほ場周辺の雑草はしっかりと除草しましょう。
ナメクジ
ナメクジ
特徴
花や葉に穴が不規則にあいて,光沢のあるスジが残ります。草花から野菜まで広く寄生します。梅雨時や多湿な条件を好み,昼は鉢の裏や枯れ葉の下に潜んで夜になると活動します。
対策
被害にあったら,周囲の鉢の裏や落ち葉の下を確認し,発見したら捕殺します。すみかになる落ち葉などを取り除きましょう。イチゴは果実が地面すれすれに成長するので食害に合いやすいので注意が必要です。周囲に湿気の多い場所がないように環境を改善します。
アオムシ
アオムシ
特徴
アブラナ科の野菜の害虫で,モンシロチョウの幼虫です。成長すると3cmほどの大きさになり,葉を食害します。摂食量が多くそのまま放置すると葉脈を残して全て食べ尽くされてしまいます。暖かい地域では4~6月と9~11月の年2回,涼しい地域では夏に多く発生します。
対策
モンシロチョウが飛んでいたら,卵を産み付けている可能性があります。日頃から葉の表と裏をよく観察します。卵や幼虫を発見したら捕殺します。植物全体を防虫ネットで覆い,チョウの産卵を物理的に防ぐ方法もあります。
コナガ
コナガ
特徴
成虫は葉の裏に産卵します。生まれてすぐの幼虫は頭部を葉肉に突き入れて食害します。12mmほどに育った幼虫は葉の裏から表皮を残すように食害します。幼虫は,アシナガバチやドロバチのエサになります。
対策
発生適温は20~25℃で,春と秋に発生が多くなります。発生初期に薬剤散布を行います。食害された場所の付近にいる幼虫を発見したら捕殺します。植物自体を防虫ネットで覆い成虫の産卵を防ぐ方法もあります。